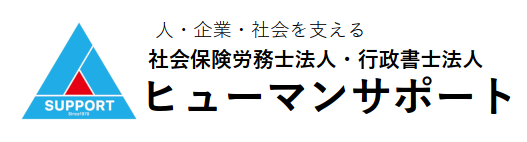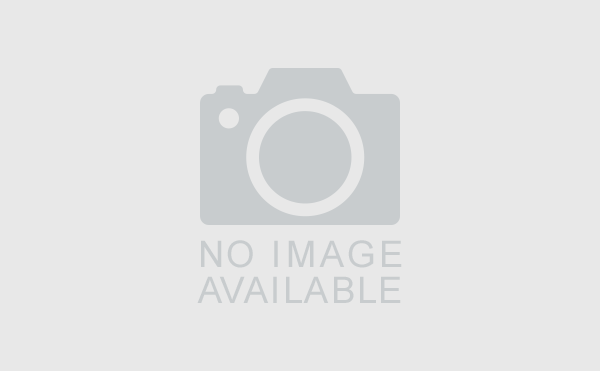出生後休業支援給付金が創設されます
令和7年4月より育児・介護休業法が「子の看護休暇の見直し」など多くの改正があり、事業主は就業規則(育児介護規程)の改正などに取り組まなければなりません。
また雇用保険法も改正され、現行の「育児休業給付金」「出生時育児休業給付金」の支給を受ける方が一定の要件を満たすと、新たに「出生後休業支援給付金」の支給を受けられるようになります。
●要件
・被保険者(本人)……「子の出生日等から8週間(女性で産後休業した場合は16週間)経過の翌日までに通算して14日以上(出生時)育児休業給付金が支給される育児休業を取得したこと。
・被保険者の配偶者…「子の出生日等から8週間経過の翌日までに通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、「配偶者の育児休業を要件としない場合※」に該当していること。
※配偶者の育児休業を要件としない場合
①配偶者がいない
②配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
③被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
④配偶者が無業者
⑤配偶者が自営業者やフリーランス
⑥配偶者が産後休業中
⑦1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
・被保険者が父親であれば、妻は主に上記④~⑥のいずれかに該当しますので、被保険者
本人が要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給対象となります。
●支給額
・休業開始時賃金日額×対象期間内の休業日数(上限28日)×13%
●支給申請手続(添付書類)
| 配偶者が育児休業等を取得した雇用保険被保険者の場合 | ①世帯全員の住民票(続柄有り)の写し等、被保険者の配偶者と確認できるもの ※支給申請書の「配偶者の被保険者番号」欄を記載 |
| 配偶者が育児休業を取得した公務員 | ①世帯全員の住民票(続柄有り)の写し等、被保険者の配偶者と確認できるもの ②配偶者の育児休業の取得期間を確認できるもの ※支給申請書の「配偶者の育児休業開始年月日」欄を記載 |
| 配偶者の育児休業を要件としない場合 | ・それぞれの理由により戸籍謄(抄)本や住民票、課税証明書等を用意 ・配偶者が妻の場合、「母子健康手帳」、または「医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書」の提出 ※支給申請書の「配偶者の状態」欄に該当する番号を記載 |
●まとめ
この他に2歳未満の子を養育する為に所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金低
下するなど要件を満たした際の「育児時短就業給付」の支給も始まります。
育児・介護関係は法改正が多い分野です。労働者が仕事と育児・介護の両立が出来るよ
うに最新の改正に気を付けましょう。